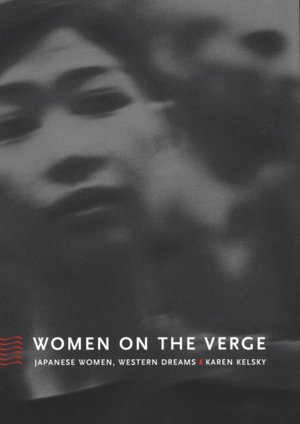
NOTE: 数ヶ月前に書いたレビューですが、今朝、コンピュータに残っていたのを見つけるまで、すっかり忘却の果てに追いやられていました。かなり時間かけて書いたのに・・・。書評だから今更ですが、アップします。
海外在住もかれこれ12年になる私は、カレン・ケルスキーのいうInternationalist というカテゴリーに属するひとりに多少なりともあたるのだろうか。著者が探求する西洋への「憧れ」というキーワードは若い私の脳裏にあったとは思うが、私のその後の人生を変えるほど大きなものだったのだろうか。私の人生の選択は、ひょっとするとより大きな流れのなかでなされてきたのだろうか、という疑問を抱きながら、本著を読み進めた感想を書いてみたい。
著者カレン・ケルスキーはイリノイ大学の文化人類学および東アジア学の助教授。
まず、本著の構成。序章では研究対象がどういった思想的枠組みのなかで捉えられるかが提示される。日本人女性の西洋に対する「あこがれ」を通して現代の日本人女性の西洋および日本に対する意識を検証することが研究対象であることが示され、かなり専門的な内容だが、方法論が語られる重要な部分である。著者がインタビューする女性は「大半が高学歴で、都市居住者、ほとんどが独身のキャリアウーマン、年齢は20歳から45歳」。すべての日本人女性が対象ではない。
第1章では、19世紀中頃から戦後のアメリカ軍による占領時代にかけての日本における女性の国際化の系譜が「憧れ」をめぐって検証される。津田梅子や彼女の教え子である三島すみえ(My Narrow Isle: The Story of a Modern Woman in Japan (1941))の著作や手紙を読み解きながら、渡米と渡米後の経験に即して、日本および西洋に対する意識を検証する。
2章では、戦後、「国際派・国際主義者」の女性たちが書いてきた著作などをもとに、国際派ナラティブがどのように発展していったかを考察する。
さらに、第3章は、現代の日本における白人男性のつくられたイメージを、広告やメディアを通して検証する。白人と日本人がお互いに抱いている、ステレオタイプ化されたエロチック・イメージと、その背後にあるさまざまな影響にも焦点をあてている。
第4章はいわゆる「国際派」とされる女性たちが直面する困難、さらにはそうした困難とどのように折合いをつけているのかを女性たちへのインタビューから浮かび上がらせる。
私にとってはエスノグラフィという分野は未知なので、本著を読んだ後はちょっと戸惑った。いろいろな側面を提示されたにもかかわらず、その現実に対する批判や問題解決がないことに対する戸惑いなのだけれど、多様な環境や歴史的事実、アクターの思いや経済的状況など、さまざまな局面が交差する現実というのは、実際に簡素化して語れるものではない。エスノグラフィは社会的現象の複雑性、相互性という深みに気づかせてくれるものでもある。読み手の関心により、それぞれの側面をより深く探ってみると興味深い考察へと結びつく可能性を秘めている。というわけなので、私が興味をひかれたいくつかのファクターに絞って考えをまとめてみたいと思う。
・イメージと「あこがれ」
まず、internationalist narrativeというキーワードを理解しておく必要がある。これは、家父長制、男尊女卑の思想の強い日本で最初から構造的に組み入れられない、高学歴で野心をもった「国際主義者」の女性たちが使う「言い分」であり、その内容とは、日本で能力を認められない、発揮できないのなら、男女が平等に扱われる海外(西洋)に出て自由を謳歌しながら、海外の人たちと付き合ったり、海外企業に職を求めたり、留学を通して自分を磨くことが許される、というものである。こうして西洋との接触を通して磨かれ、探し当てた自らは「新しい自分」であり、封建的価値が残る「古い日本的伝統」のなかでは決して見出し得ない「真の自分の姿」である。つまり、西洋という鏡を通してはじめて、「国際主義者」を名乗る女性たちは自己を確立する、といえるのだが、厳密にいえばこの「西洋」というのは、「西洋というイメージ」であることが明らかにされる。
ここで、「イメージ」という非常に重要なキーワードが出てくる。イメージとは、実際の姿ではなく、ある程度実際の姿に「自らが見たいと思うもの」=「あこがれ」を投影しながら作られる姿である。日本社会の「後進性」に幻滅した国際派の日本人女性は、「救世主」としての西洋および「西洋人男性」のイメージのもとに、日本を脱し、海外に出ていく。それは実に積極的なるdefect(「棄国」という言葉があるが)であり、後戻りはできないという覚悟とともに人生を大きく変える選択でもある。
同時に、捨ててきたものに対するビターな感情は、日本の社会や日本の男性そのものへと向けられ、その反動として向かった西洋でこうした主張を買う西洋人男性やメディアを通し、イメージが広まる原因となる(「世界一魅力のない日本人男性」、「世界一魅力的な日本人女性」、あるいは「日本人男性は女性を喜ばせられない」、さらには「イエローキャブ」というレトリック)。
このイメージは「国際主義者」の日本人女性の占有物ではない。著者は、国際派女性の、あるいは西洋人男性の日本人男性に対するイメージ(非常にネガティブなイメージ)、あるいはそれを煽ってきた日本や海外のメディアにも焦点を当てる。
ここで気付くのは、「国際主義者」の日本人女性をはじめ、一部の西洋人男性、日本人の西洋に対するあこがれを煽り続けてきた日本のメディア(“seling of white men as commodity markers of upward mobility, 187)、旅行産業、外資系の会社や留学エージェンシーやサービスなど、さまざまなアクターがその西洋の「イメージ」と「リイマジンドされた西洋と西洋人」を自らの利益に都合のよいように利用してきた事実である。私としては、このうちで日本のメディア、旅行産業がとりわけ「PR」効果という側面を重視してることを考えると非常に問題を感じる。
・日本人女性と西洋男性のあいだのロマンス、消費主義の行きつく先・・・
日本人女性と西洋男性のカップル、西洋人女性と日本人男性のカップルをみると、数からして明らかに前者が多い。この事実を不思議に思う人は多いし、どうしても単なる偶然であるとは思われない。かくいう私と夫も前者例にあたるのだが、巷に転がっている理由は、基本的にネガティブなものが多いこと(たとえば、日本人にはモテない日本人女性とルーザー外国人との結婚、など)、さらに結局は個人間の関係性は私たち固有のものである、という気付きから、どこかでこの問題は「取り扱うに足らず」と認識してきた、というのが妥当だという気がする。
大学卒業したころの私はケルスキーの研究対象のような上昇志向をもった野心的な「国際主義者」の日本人女性では決してなかったし、今もそれは変わらない。私のなかにあったのは、海外への憧れ、というよりは、日本社会における居心地の悪さ、であったと言うのが最もしっくりくる。日本社会では私のもつあまりに個人主義的、自由主義的(あるいは社会主義的)な価値観はいずれ衝突を来たすであろうことを肌で感じていた。経済的には何の問題もなかったが、思想的な行き詰まりの予感は実にあった。そんなときにカナダ人の(今の)夫に出会った。なので、私はケルスキーの調査対象に当てはまらないと思われるが、トロントで国際結婚している日本人女性を見渡してみても、ケルスキーの調査対象に当てはまる人はほとんど見当たらない。そこで思うのだが、「彼女たち」は一体、誰なのか。
本著を読む限り、この「国際主義者」の日本人女性は、ひとつの見方をすれば女性の伝統的役割を押し付ける日本社会に対する抗議者であるが、同時に極度な日本の消費主義の行き着く末としての、「カニバリズム的」消費者でもある。つまり、海外旅行やブランド品を追いかけた末に、最も手に入りにくい欲望の対象としての「外国人ボーイフレンド」は、彼女たちにとっては最後の砦なのである。
この「国際主義者」として描写されるふたつの像が、私にはどうも腑に落ちない。日本社会に対する抗議者でありながら、日本の過度な消費主義を無批判に鵜呑みにする、という状況に、思想的な二律背反を感じるからである。具体的に言うと、日本社会の構造的差別には抗するが、際限なき消費欲を満たすために海外へ出て、自分の置かれた地位を利用し「搾取」に精を出しているのである。「外国へ目を向けることは、おそらく日本社会で女性の伝統的生き方への期待に抗する、最も重要な手段であるのではないか」(序章)とケルスキーは言うが、この「抗し方」がまるで徹底していない、と感じられてならない。
・植民地主義と消費主義
ケルスキーが指摘するように、国際派の日本人女性が海外に出ていく現状は、彼女たちの経済的パワーに裏付けられている。いくら社会的制約は厳しいといってもOLはそれなりの給料をもらっているわけで、その経済力を海外で利用する(留学、遊学、語学研修、旅行)力を備えている。たとえば、女性の地位が非常に低いインド社会を例にとってみると、インド社会の女性たちは現状から脱出するための経済的手段を持たない。日本人女性が「息抜き」として海外に出ていける背景には、日本経済という大きなバックアップがあってこそなのだ。これは国際派の日本人女性もよく心得て利用している「力」である。この事実は、日本という国で「力」を奪われマージナライズされた女性が、海外では発揮できる「力」という意味で非常に興味深い。さらには、ポスト・コロニアリズムの影響、オリエンタリズム(サイード)の影響を無批判に受け入れ、日本およびアジアの女性に対するイメージを描いている西洋男性(the commodification of the Japanese women)を受け入れることとなる。
同時に、日本が連合軍(なかでもアメリカ)に敗戦したという歴史的事実も、日本人の西洋へのあこがれに大きく関与している。津田梅子の時代から日本人女性を驚かせ、喜ばせてきた「レディ・ファースト」の西洋文化のイメージは、アメリカ進駐軍GIの存在を通して一般の女性たちの間にも浸透していくことになる。実際、アメリカ進駐軍が敗戦後の日本に来たという事実は、日本人に大きな心理的影響を与えたし、その影響は見えない形で未だに尾を引いている。
・国際化という神話。日本社会の変革までは思いが至らないエゴイスティックな国際主義者
人類学者のケルスキーは、さまざまな側面を提示してくれるが、あからさまに彼らの関与を批判することはない。ただし、フェミニストを自称する彼女は、日本での低い立場に不服を申し立てる手段、レジスタンスとして海外に出た日本人女性が、日本で女性の地位向上を目指すための連帯した運動には結びついていない事実に対してだけは批判の矛先を向ける。
時代をさかのぼって見れば、津田梅子や三島すみえ、加藤シヅエなどは日本帰国後、アメリカにおける男女平等社会を日本に取り入れようと尽力してきた。あの当時の様相を思い合わせると、周囲の酷い反対にあいながらも女性のための学校を作ったり女性の地位を向上させるための法案を通すために働いたりしてきた彼女たちの努力は並大抵ではなかっただろう。
一方で、現代の「国際主義者」の女性たちはどうだろう。日本社会の構造を変えようという意図は少しもなく、日本社会から脱した自分と自分が入った文化を理想化することに終始している。極端な例はマークス寿子(「大人の国イギリスと子どもの国日本」)や斎藤澪奈子(「超一流主義」)で、日本に蔓延する一部ヨーロッパのイメージを誇張した挙句、レイシズムまで使って自分の主張を繰り返していて、私はベストセラーとなったらしいこの本の内容を知り、唖然としてしまった(”Japanese and Arabs are scavenging up the hotels of English girls finishing school… What kind of finishing school is it where you only hear Arabic and Japanese spoken?!” “There are no more real English girls... Instead… they are full of Arabs and Japanese. In such an atmosphere, can anyone learn true manners? To put it bluntly, can anyone even learn to speak proper English.P125)。このような人種差別的で偏見に満ちた本がベストセラーになる背景には、ジャーナリズムの質の低さや差別に対する研ぎ澄まされた感性の欠如があるだろうと思う。
このような現実を見るとき、最後に疑問が出てくる。一体、彼女たちは本当に国際派と言えるのだろうか。日本は国際化したのだろうか、という疑問である。
日本人にとっては「国際化」という言葉は、殺し文句にも等しい。当時から言われていたことだが、言葉の中身は空っぽで、誰も「国際化とは何なのか」という問いに満足に回答を出すことはできなかった。言語(英語)習得ではない。結局、ナショナリズムの影響を振り切ることができず、まず日本人として日本文化を知り、日本人としての教養と知識を身に着けることだ・・・とか何とかひねり出してきた最もらしい答えは、日本人の趣向にはあったようだ。
過去、「国際化」の掛け声とともに、英語学習ブーム、海外旅行ブームが広がったり、西洋を日本人の文脈で読んだり、日本を特殊な外国人の文脈で読んだり(アレックス・カーなど)、同時にまったく逆に今度はねじれ切って日本文化を絶対視するナショナリズムなどが出てきたが、すべて何かおかしいような気がする。
津田梅子や加藤シヅエには西洋文化の、具体的にどの部分が、どの社会的構造が、どの法律が日本には欠けていてそれを導入することによって日本人女性、ひいては日本社会がよりよい社会になるという確信があった。そういう意味で、彼女たちはフェミニストであったし、真に理想の日本像を捉えることのできたリーダー的人物だったと思うが、斎藤澪奈子やマークス寿子などはエゴセントリックなキャピタリストでしかない。こうした論客は少し突いてみれば、人種差別や排他主義、ナショナリズムの思想的断片がぞろりぞろりと姿を現すことだろう。現代に生きる私たちは、彼女たちが崇拝するような西洋的価値に根ざしたグローバライゼーションやグローバル経済という現実を無批判に受け入れるべきではない。
日本を出て以降、ことあるごとに感じてきたのだが、日本が長年抱えている問題のひとつは、リーダーシップの不在に違いない。政治の世界でも産業界でも、教育界でも、どんな分野でも、将来、こういう形に導いていきたい、というイメージをもってそれを周囲の人たちに信じさせ、エンパワーしていく情熱とスキルを持った人が育っていない。「国際化」にしても、そのフワフワしたイメージだけを売り物にして(資本主義がそれを食い物にして)、中身を詰めてこなかった日本はInternationalizationに実質、乗り遅れてきた。
あるいはこう言うこともできるだろう。多くの日本人は、日本には国際化は必要ない、あるいは国際化は「百害あって一利なし」と、実は無意識のうちに信じてきたようなところもある。でも、最もお金をもっている若い女性のために、日本の産業がよってたかって国際化をファッションとして売ってきたという一面もあると思う。つまり、80年代から言われてきた「国際化」は、日本が国運をかけて取り組んでいく必要のある問題ではなかったのだろう。
・ 最後に、再びイメージについて
だからこそ、「イメージ」という概念がカギになる。ケルスキーが第3章Capital and the Fetish of the White Man で省察するように、日本のコマーシャルには白人男性が大活躍している。こうしたコマーシャルに乗って、若くて野心的な日本人女性が信じてきた西洋のイメージ、旅行会社やファッション業界が売り込みに懸命になっている西洋や西洋文化のイメージ、はたまた国際結婚エージェンシーが売り込む西洋男性のイメージ・・・、これらは実際には、私たちを中身のない幻想へと導く資本主義の道具に過ぎないということを見破る必要がある。
実は、私も異文化に暮らして思うのだが、この「イメージ」というのは私たちのコミュニケーションに計り知れない意味をもっている。例をあげると、私にも「インド人」のイメージや「ドイツ人」のイメージを持っているし、こうしたイメージはそのイメージから例外的なインド人を友達に持っていても未だに根強く残っているほどだ。一方では、西洋ではある「日本人女性」のステレオタイプ(イメージ)が蔓延している事実に気付かされる。このステレオタイプはマダム・バタフライからイエローキャブまでさまざまだが、自分ではまったく関係ないと思っていた自分がそうしたイメージに影響を被るというのは事実である。
異文化に暮らす経験の真髄は、この私たちが知らずに持っている「イメージ」が繰り返し繰り返し破壊され、新しく作られては破壊され・・・、という経験の連続である。最近の私は、こうした経験を繰り返すなかでしか、自分以外の他人とお互いにより深い理解に近づくということはないのではないか、と思う。言い方を換えれば、自分の持っている「イメージ」に固執した他者とのかかわり方に創造的で発展的な意味はない、ということである。
本著が出版されてすでに10年が過ぎているが、日本の状況はどう変わっているのだろうか。「国際化」の内情が実は「空洞化」であったなど、誰が信じるだろうか。しかし、私たちはよりものごとの表層に現われない部分を見る必要がある。
No comments:
Post a Comment
コメント大歓迎です!